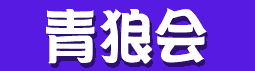 |
|---|
Endless sorrow |
|---|
|
君にもし 翼が ひとつしかなくても 僕にもし 翼が ひとつしか残ってなくても |
***** ***** *****
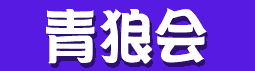 |
|---|
Endless sorrow |
|---|
|
君にもし 翼が ひとつしかなくても 僕にもし 翼が ひとつしか残ってなくても |
***** ***** *****
2001年5月24日付朝日新聞より
首相に語った元患者の手記
「私たちの訴えを聞いてから判断して」。23日に実現したハンセン病訴訟の原告9人と小泉純一郎首相の面談は、予定を大幅に上回り40分近くに及んだ。午後4時、弁護士とともに首相官邸に入ると、首相は一人ずつ全員の手を両手で握った。熊本県の療養所で暮らす西トキエさん(71)や日野弘毅さん(67)が、家族から引き離された半生をつづった手記を読むと、首相はハンカチで目を押さえたという。
−−−−−−−−−−−−
熊本県 西トキエさん
−−−−−−−−−−−−
ハンセン病と診察されたのは、昭和24年、19歳のときでした。療養所に行くと決心した晩、お父さんは「やらん」「残念だ」と言ったきり、ものすごく泣きました。お母さんも「ひとり娘なのに」と言って、3人で泣いて泣いて一晩過ごしました。
お父さんは、毎年面会にきてくれました。来るたびに「まだ帰れんか」と聞いていました。入所して10年以上もたったころ、お父さんが「養子をとる」と言いました。「仕方ないな、自分が帰れんから」と思いました。でも「これで、ふるさとには帰れん。自分が跡取りだったのに」と思うと泣けてきました。
昭和62年、お父さんが死にました。電話でお母さんは「帰ってくるな」と言いました。でも帰りたかった。
何とか、お通夜に、間に合いました。
遺体に「ごめんね、ごめんね」と言って泣きました。お葬式では、わたしは一番後ろでした。わたしがお父さんに近づくのを、養子も、親戚も嫌いました。
その後、お母さんとたまに電話で話すことが出来ていました。でも、10年くらい前、親戚から電話があり、「もう電話もかけてくれるな」と言われました。
それきりお母さんと連絡はしていません。
お母さんと会いたい。でも生きているのか、死んでいるのかも分かりません。
ひとこと、「お母さん」と呼びたい。でも呼べないわたしです。
今度の判決でやっと救われました。
どうか、わたしをふるさとに帰してください。もう長引かせないでください。お願いします。 (抜粋)
−−−−−−−−−−−−−
鹿児島県 日野弘毅さん
−−−−−−−−−−−−−
昭和24年、16歳で入所して以来、ずっと療養所の中におります。
私にも愛する家族がありました。
昭和22年の夏、突然保健所のジープがやって来ました。私を収容にきたのです。母はきっぱりと断ってくれました。ところが、ジープは繰り返しやってきました。昭和24年の春先、今度は白い予防着の医師がやってきて私を上半身裸にして診察したのです。
その日から私の家はすさまじい村八分にあいました。18歳だった姉は婚約が破談となり、家を出なければならなくなりました。
小学生の弟は、声をかけてくれる友達さえいなくなりました。弟がある日、母の背中をたたきながら「ぼく病気でないよね」と泣き叫んだ姿を忘れることはできません。
このまま家にいればみんながだめになると思い、自分から市役所に申し出て、入所しました。それなのに家族の災厄はやみませんでした。
それから20年あまり、母が苦労の果てに亡くなったときも、見舞いに行くことも、葬儀に参列して骨を拾うことも、かないませんでした。
18の時、家を飛び出した姉は、生涯独身のまま、平成8年、らい予防法が廃止になった年の秋に自殺しました。姉の自殺は母の死以上に、私を打ちのめしました。
姉の思い。母の思い。いまだに配偶者に私のことを隠している弟、妹の思い。そのために、私は訴訟に立ちました。
判決の日、私は詩をつくりました。
太陽は輝いた/90年、長い長い暗闇の中/ひとすじの光が走った/鮮烈となって/硬い巌(いわお)を砕き/光が走った/私はうつむかないでいい/市民のみなさんと光の中を/胸を張って歩ける/もう私はうつむかないでいい/太陽が輝いた (抜粋)