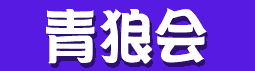 |
|---|
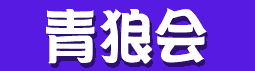 |
|---|
恋をしちゃいました! |
|---|
この曲を聞く時に合うと思われる文章
推奨BGT(バック・グラウンド・テキスト)
***** ***** ***** 渡辺京二著『新編 小さきものの死』(2000年1月、葦書房発行)から
序詞 小さきものの死
もう十年以上も昔のことになるが、私が田舎の療養所にいた時分、隣りの病棟の斜め向いあたりの部屋で母と娘が一晩のうちに死んだことがあった。
その頃私はかなり大きな手術の後で寝台の上に身動き出来ずにいたが、窓にそって立つあかしやの裸木の細く組み交わされた枝の間から、びっしりと水滴のように星が見えた或る晩、私は断続する不思議な声を聞いた。それは最初笑い声のようにも聞こえ、隣棟の個室でまた女患者たちがカード遊びなどに興じているものと深く意にも留めず、私は本を読み続けて行ったが、その内それは私の耳の中でまぎれもない泣き声となって鳴り始めたのだった。
しかし、それはその後でも私が繰り返し疑ったようにいかにも笑い声に似ており、世の中にそのような奇妙な泣き声のあることを、その時私はほとんど初めて知らされる思いをした。それは長く続き、私がおそい眠りに就くまで続いた。その声には確実に私を脅かすなにものかがあった。このようにも女が泣く。しかしまだ一年に満たぬ療養所暮しの見聞によっても、私は患者が病苦の故にはそのように泣かぬことを知っていたので、自然私の想像に導き出されるのは男女の愛憎に関する葛藤であった。この種のことなら療養所の日常にすぎぬ、たとえそれが笑うべきことではないにしても。そう思い私は眠った。
翌朝、私は事実を知った。昨日天草の一農村から極度に衰弱した母娘がこの療養所に送りこまれた。付添ってきた父親はそのまま送ってきた車で立ち去った。母娘は二人部屋に入れられたが、夜に入って母親の容態が悪化した。そして娘が泣き始めた。どちらが先に死んだのか、もう私は憶えていない。とにかく明け方までに二人とも死んだ。
この話を看護婦の抑揚の利いた口ぶりで聞かされた時、私は鮮やかにひとつの光景を見た。死にかけている母親の痩せた腕が機械じかけのように娘の体をさすっている光景を。そしてこの母親は娘もまたすぐに死ぬであろうことを確実に知っている。この光景が与えた衝撃−−いやそれはもっと鈍い、浸みこむような感じのものだったが−−は実に奇妙で、今でも私は忘れられない。それは何ともいえぬいやな感じだった。
父親の没義道さとか、農村の暗さとか、社会の不合理だとかではない。それへの怒りは無論のことにしてもそのいやな感じはもっと根本のところに係わっていて、その根本の事実がいかにも理不尽であった。人はこのようにして死なねばならぬことがある。この事実はまだ少年といってよかった私には震撼的だった。少年の直覚は、こんなことはあってよいはずがない。許されてよいはずがないと叫んでいた。
これは十二年昔の話である。一年も二年も待たなければ療養所に入れなかった時代のことである。今はこういうことはない。療養所の空床化が問題となり、患者の大半が軽症であるのが今日の現実である。ただ私はあの母娘がそういう風に死なねばならなかったという事実を消しうるものはこの世に何もないと思うだけである。私は彼女たちの出棺をその朝見たように思う。病棟の端の出入口から看護婦たちによって棺が運び出される。それを雑役夫が手押し車に乗せて、草の中の路をコトコトと押して行く。そういう出棺の姿を私はいくつも見た。その朝は霧雨が赤枯れた草を濡らしていたと思う。あるいはこれは別な日の光景が誤って結びついているのかも知れない。私は母娘の出棺など本当は見なかったのかもしれない。ただ私はひとつの光景は確実に見た。それは前に書いた、死にかけた母親の腕が機械か何かのように娘の体の上を行き来している姿である。東四病棟の何号室かとして今も残っているその病室を私が訪ねてみて、戸を引き開けた途端、並んだ寝台の上に死にかけた母と娘の体が今もそのまま横たわっているのを見出す、という幻想が時たま私の脳裏をよぎることがある。(後略)
「小さきものの死」 初出 「炎の眼」11号(昭和36年(1961年)12月)
***** ***** *****